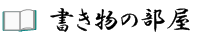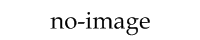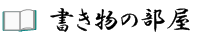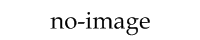いつもお世話になっている  と言うサイト(2007/12閉鎖されました)がありまして、 と言うサイト(2007/12閉鎖されました)がありまして、
小説の検索がメインなのですが、依頼すれば書評もやって頂ける、ありがたいサイトです。
私の作品も書評して頂きましたので、その内容を転載させて頂きます。
|
|
|
ネコタ斑猫です。
今回の書評、少しばかり失礼な書き方になるかも知れません。
文章には破綻がありません。一つの文章は比較的短く、一段落が長すぎるということもありません。
それなのに、非常に冗長な印象があるのです。
失礼なことを申します。火曜サスペンス劇場の副音声のような小説だ、と思いました。
主人公の行動を綿々と描写しており、それはしかし親切なのか、どうか。
書き手が呈示しうる情報と、読み手が知りたい情報というのは、おのずから異なるのではないか。
書き手の中には全ての情景があります。しかしそれを全て述べ立てていては、読み手には、書き手が一体何を言いたいのかわからない。この物語で重要なのは一体どこなのか、よくわからない。全て均等にコマワリされたマンガのようなものです。物語を追うことはできますが、いささか退屈です(のらくろとかそんな時代のものやある種のギャグマンガなどにおいてはその微妙な冗長さが味わいだったりしますが…)。
全ての情景を所有し、物語の流れを知っているのは書き手ただ一人です。それをそのまま呈示することは得策ではないと考えます。ドラマティックなコマ割りのように、思い切った削減と同時に思い切った過剰も必要なのではないか。それこそがストーリーテリングにおけるメリハリなのではないかと思うのです。
と思うと同時に、むしろこれは、ある種の脚本なのではないかとも考えております。
この文章を元に役者さんが動くと仮定すると、この丹念さは逆に不可欠だと思われます。
文章のスタイルは様々あり、また実験的であってしかるべきです。
先日書評させていただいた作品と考え合わせると、これもまたその試行錯誤の一過程なのではないかと考えました。
二作品を読ませていただいた立場から申し上げますが、あの二作の中間ぐらいのスタイルで書かれたものが、読み手には丁度読みやすいのではないかと思われます。
先日の作品はかなり緩く、正直スカスカした感じですが、わりと行き当たりばったりに書かれている分、メリハリはそれなりにあったのではないか。
今回のはどうも全体的に均等に過ぎるキライがあるのですが、緻密な構成が感じられます。
そのあたりの折り合いをつけて、ほどよいメリハリ、ほどよいアドリブ、それを裏付ける構成という具合に書かれると、読み手として楽しめるものになるかと思われます。
さて、相変わらず小説世界の小道具や用語の用法などが気になるお年頃なのでございますが。
懐中時計を開いたり閉じたり角度変えたりしてるとあやしかないですか?
今日日の探偵さんはもっぱらピンホールカメラというのをご活用だそうですよ。
探偵さんのサイトを覗くだけでもそのあたりの小道具ははっきりしますので、物語を書き始める前に物語の舞台として選んだ職業などの事情は掴んでおいたほうがよろしいかと存じます。
あと、私がテキストファイルを送ってくださいといわざるをえなかったように、そちらの小説の表示方法は非常にバリアフルです。私のパソコンの解像度は1024 x 768で恐らく現在一番の多数派です。それで読みにくいとなると大勢の方もやはり同じように読みにくいと感じ、中身を見る前に遠ざかってしまっているのではないかと恐れます。
せっかくウェブに発表している小説です、大変勿体無いので、多くの方が見られるように、普通の表示方法も選べるようにしたほうがよいのではないでしょうか。
***
と。
書き上げたところで、後書きを拝読しました(書評は作品だけについて行うので読むのは後回しにしておりました)。
自主制作映画用の原案だったんですねー。
私の印象というのもあながち間違っていなかったようで…。
|
|
今回私の指名はありませんでしたが、前回の書評でお伝え出来なかった点があったので、改めて参加させて頂きますね。
前回の書評でも感じた点なのですが(ネコタさんの指摘にもあるように)、私も脚本のような印象を受けました。前作は一人称で進められている為「探偵と迷い」程明確な脚本としてのイメージがあったわけではありませんが、描写の中にはその要素が多分に含まれておりました。
私自身も(ネット上で公開こそはしておりませんが)脚本を執筆している為、小説と脚本の視点の差にいつも悩まされております。
脚本を書く感覚で小説は書けませんし、また逆に小説の感覚で脚本は書けません。
脚本というのは、小説と違って「ヴィジュアル化」されることを目的として作成されています。ですので、脚本が作品の最終形態ではなく、あくまで「作品を造り上げる上での過程」でしかないのです。
その場合重要視されることというのは、ドラマであれば監督や役者さんに「どんな作品にしたいのか」を伝えることであり、漫画原作であれば漫画家さんに「どういう漫画にしたいのか」を伝えることです。
一方、小説はというと、それそのものが「作品の完成形態」です。ドラマや映画のようなヴィジュアルから受ける感動を、文章で読者に伝えなければなりません。
私は、この両者が「混在」してしまっているような印象を木眞井さんの作品から感じました。作品のあり方が「小説」としてなのか、「脚本」としてなのか、その境界が曖昧になってしまっているような感を受けたのです。
また、脚本というものは、通常の小説に慣れている方達からみるととても「読みづらい」ものだったりします。脚本は「読者を感動させる」ことを直接的な目的として存在するわけではなく、あくまで「作品の設計図」に過ぎないからです。
もっとも、前述しましたように、私自身「小説を書く視点」と「脚本を書く視点」で、常に頭を悩ませています。 この境界は実に微妙で、かつ面倒な存在だったりもしますので。
もし、ご自身の小説作品に対するコメントで「脚本的」というものが多かった場合、一度はこの両者を切り分けて考えられた方がいいかもしれませんね。
ちなみに、私が実践しているトレーニング方法をご紹介しますと、私はひとつの場面につき「脚本」として、また「小説」としての両者で描くということをしています。それ以外にも、小説と脚本の違いを学ぶ一番いいトレーニング方法は、「既存の小説を、脚本にしてみる」或いは「既存の脚本を、小説にしてみる」ことかもしれません。これはまだ実際に試したことはないですが、いつか試してみようと思っております。
まずは、木眞井さんの中で「小説の視点」と「脚本(ヴィジュアル化が目的とされるもの)の視点」の違いを切り分けてみては如何でしょうか?
書評に直接関係のない余計なお節介的コメントですが、自分自身も悩む点なので、ついつい口を挟んでしまいました。
あくまで参考として聞いて頂ければ幸いです。
|